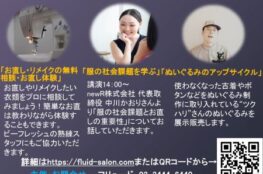早速ですが、あなたはフリマアプリ(フリーマーケットアプリ)を使ったことがありますか?
フリマアプリ前身の、ネットオークションサイトの始まりは1990年代。
そして2013年頃からのスマホの普及により、フリマアプリが急成長を遂げています。
これらのサービスの出現によって、不要になった物や、欲しい物も簡単に売買できるようになりました。
大変便利なので、活用されている方も多いのではないでしょうか?
出品した物が、思わぬ高値で売却できたら嬉しいですよね。
また、思いがけない掘り出し物を購入できた時も同様でしょう。
ほとんどの人は「いらないものがお金になったら良いなぁ」ぐらいに考えているかもしれません。
しかしフリマアプリを利用することで、循環型社会に貢献しているのはご存知でしたか?
何気なく使っていても、これが思いのほか貢献しているんです。
ここで少し見てみましょう。
Contents
フリマアプリと循環型社会の関係とは?
フリーマーケットとは?

まずは、フリマアプリと循環型社会を見てみる前に、フリーマーケットの発祥を見てみましょう。
フリーマーケットの発祥は、フランスと言われています。
前身であるガラクタ市やボロ市など、公園や競技場などで催したのが始まりです。
いつしかこれらの市場の文化は、アメリカ等にも広まりフリーマーケットと呼ばれるようになります。
元々はフリーマーケットのフリーは「FLEA」、つまり”蚤”(ノミ)の意味です。
語源は諸説ありますが、ノミの意味から始まり、汚らしいやみすぼらしいなど、ネガティブな意味で捉えられています。
また時代の流れによって、自由市場という意味での「FREE MARKET」が使われる事も多くなりました。
FLEA(蚤)よりもFREE(自由)の方が、クリーンなイメージですよね。
おそらくほとんどの人は、フリーマーケットといえば、FREEのほうを思い浮かべるでしょう。
アメリカやヨーロッパなどでは、フリーマーケットが昔から頻繁に、開催されてきました。
しかし反面、日本のようなフリマアプリの利用度は浸透してません。
フリーマーケットが発達しているため、アプリの必要性がないのでしょう。
対面式のCtoC文化(一般消費者と一般消費者)が根強く残っており、コンビニもなく配送手配などの問題も、その要因と言われています。
”循環型社会とは?”

前置きが長くなりました。
では、フリマアプリと循環型社会を検討してみましょう。
循環型社会とは廃棄物を減らし、資源を循環させながら利用していく社会を言います。
大量生産、大量消費、大量廃棄になった現代は、人間の便利さの追求と同時に、環境に対する配慮も必要です。
環境問題は、現代社会において避けては通れないテーマで、その一つの解決策が循環型社会なのです。
循環型社会には、以下の取り組みが大切です。
リデュース(Reduce)減らす
リユース (Reuse)再利用する
リサイクル(Recycle)再生利用する
上記の頭文字のRで”3R”(スリーアール)と言われています。
この流れは世界的なもので、日本では環境省を中心に3Rの社会を企業や個人に推奨しています。
*ファッションの3Rについては
をご覧下さい
フリマアプリは「いらないものをお金に変えよう」というイメージが、強いかもしれません。
確かにテレビCMを見ると”何でも売れる”の文字が並びますので、そう思ってしまうのも当然です。
しかし、フリマアプリの利用により循環型社会に貢献している事が、ここでぼんやりとイメージできたでしょうか?
フリマアプリの副産物?
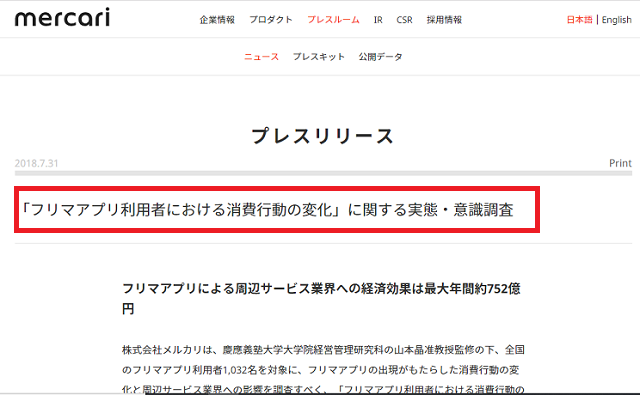
昨年フリマアプリの大手メルカリが、「フリマアプリ利用者における、消費行動の変化」の実態・意識調査を発表しました。
これはフリマアプリが社会に浸透することによって、どのような経済効果があるのかを調査したものです。
(例えばフリマアプリに出品するためには、お直しをする必要があるかもしれませんし、郵送するためには包装用紙が必要になります。 フリマアプリ利用者1032名調査)
これによると、フリマアプリに出品する前後に、使う機会の増えたサービス調査では、
1位 クリーニング (洋服などをきれいな状態にして出品)
2位 お直し (出品する物をリフォーム、リペアして出品)
3位 ホームセンター(ハンドメイド・DIY資材購入して出品)
となっています。
2位にお直しのサービスが入りますが、これは何を意味するのかというと、
「まだ使えるモノは、修理して出品してみたい」
との意向の反映でしょう。

そして意外なことに年代別にみると、20代が51.9%ともっとも高く、30代で43.4%、40代で39.1%です。
なぜ20代の若年層に、リサイクル意識が高いのでしょう?
その答えは、育ってきた時代背景にありました。
不安要素が循環型社会を作る?
 現在の20代は、ネットやスマホで消費することに慣れている、デジタルネイティブ世代。
現在の20代は、ネットやスマホで消費することに慣れている、デジタルネイティブ世代。
生まれたのは、バブルが崩壊した1990年以降。
日本の景気低迷期から、2008年の大手証券会社リーマン・ブラザーズの破綻による世界同時不況に育ちます。
そのため、モノはあふれているけれど、なんだか将来は不安、という意識が強いのです。
日用品は100円ショップ、ファッションはファストファッションが、生活に定着している時代でもあります。
バブル時代のように高級ブランドを頑張って購入はしません。
ブランド品は、サブスクリプションサービスで必要な時だけ利用すれば良いからです。
※サブスクリプションにつきましては
をご覧ください
また、中古品に対する抵抗感はなく、ネットやスマホで情報収集し、効率良く売買する。
保有するよりも、賢くシェアする事を考え行動しています。
まとめ
現代の価値観は、大切な物を売買したり共有する事がスマート・ステイタス。
そのニーズに応えたサービスを展開した、フリマアプリ。
不用品を廃棄せずに、フリマアプリに出品し売却する事で、循環型社会のリユースに貢献しています。

 業務のご案内
業務のご案内